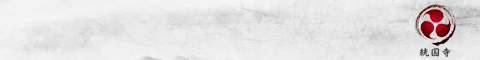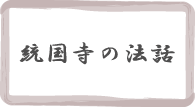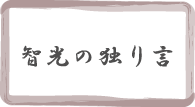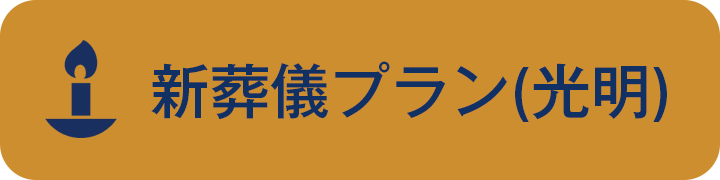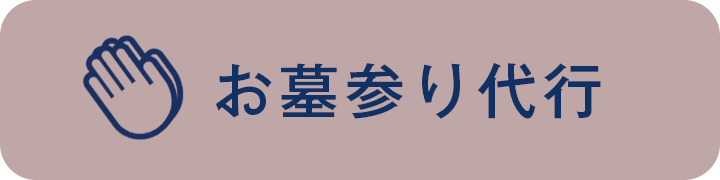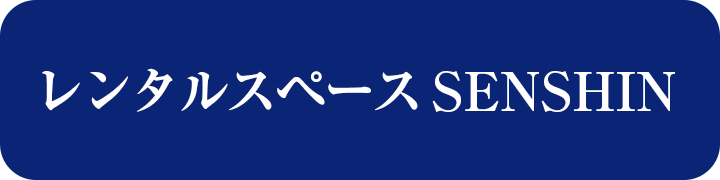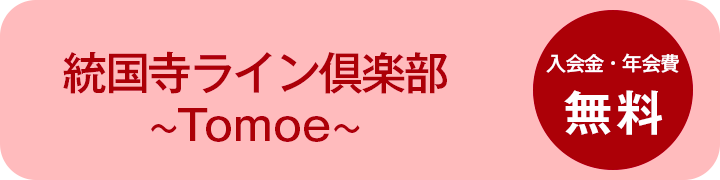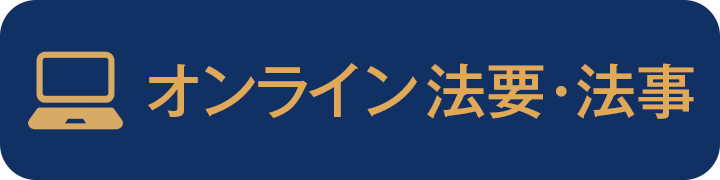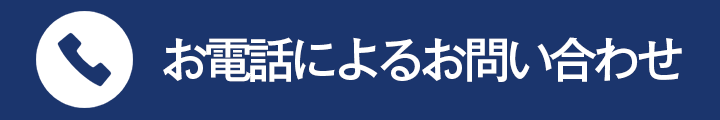『遊心安楽道』その一
元暁大師が7世紀に著された『遊心安楽道』について書く。
そのためには、まずいわゆる偽撰説を科学的に批判する必要があるだろう。
『遊心安楽道』は審祥、義天、良忍、法然、明恵などの高僧が元暁撰としているにもかかわらず、近年に至って(1960年頃〜)、元暁仮託の偽撰説、すなわち元暁が書いたものではない(より正確には元暁を信奉している僧の誰かが元暁の名を使って書いた)という説を実しやかに主張する学者が現れている。
これらの学術的主張はまず、『遊心安楽道』を文献的に考察し、元暁が生きた時代になかったと現在までは推定される文献が著書に入っているがゆえに、元暁撰ではないと主張している。しかしながら、社会科学的には元暁偽撰「説」は一つの主張であって、その主張が証明されたわけではない。
そして偽撰説という主張は、一介の説という位置付けを脱し、完全な証明に至ることはできない。
なぜならば、これは「悪魔の証明」に似たジレンマに陥るからである(※「悪魔の証明」の定義についてインターネットをご検索ください)。
つまり審祥・義天・良忍・法然・明恵などの高僧が元暁撰と認識していた点、元暁撰と記している写本が存在している事実、7世紀に訳出されていなかったとされる文献がすでに新羅に入っていた可能性(※サンスクリット版は7世紀にすでに存在)などを踏まえると、『遊心安楽道』が本物ではないという証明に至ることは難しい。
また現在に至っては『遊心安楽道』の原本が存在せず、直接的な筆跡鑑定が不可能であり、当時の文献引用の矛盾点を指摘しても、後世の挿入や写本の誤りという可能性を完全には否定できない。換言すれば、作者の帰属問題をともなう偽撰説はどこまでいっても偽物ではないか、という推測に基づく主張の枠を越えることはないのである。
またこれらの主張は、「還元主義」であると批判することも可能である。
還元主義とは事象を構成する部分とその相互作用が、その全体の事象とイコールであると考える研究手法に対する批判である。偽撰説はまさに『遊心安楽道』の構成要素に、現時点では元暁の生きた時代に存在しなかったと考えられている文献からの引用があるがゆえに、『遊心安楽道』という全体自体の価値が失われたかのような印象を与えている。
しかしながら、一構成要素によって全体を否定することは還元主義にあたる。
『遊心安楽道』の一構成要素が、『遊心安楽道』全体に通底する内容と価値―すなわち元暁の浄土思想と実践方法が記され、浄土教が宗として成立すると明らかにした点と、その後良忍、法然などの日本浄土宗の祖師たちがこの『遊心安楽道』を引用し、自らの宗派を興すに多大な影響を受けたという点―、は失われないである(※『浄土三国仏祖伝集』では元暁は祖師(慈愍流の初祖)の一人として数えられるなど非常に高い位置付けであったことがわかる)。
さらに言えば、元暁仮託の偽撰説には決定的な欠陥がある。
偽撰説が事実であったとすれば、なぜその著者は自分の名前を書かなかったのであろうか。通常、本であれ論文であれ、それを書いた著者は自分の名前を単著者/共著者/編者などと明記する。なぜ自分の名前を書かず、元暁と記したのか。
この問いに対して、偽撰説は推測に基づく答えしか提起できていない。元暁撰と書かれている場合、その文字通り、元暁が書いたものと認識するのが普通である。あるいは元暁撰と書かれていれば、仮に後世の僧の誰かが追補などをしたとしても、そのベースは元暁が書いたものと認識するのが普通である。百歩譲って、仮に他の誰かが元暁の遊心安楽道を編集したとしても、その著者の認識としてはそれは元暁が書いたものを修正・追記したがゆえに(実際に遊心安楽道のベースは元暁の無量寿経宗要)、元暁撰と書いたというのが至極当然の解釈といえよう。
しかし偽撰説を唱える学者らは、この当然の解釈(1960年頃に偽撰説が唱えられる前までは主流)について、文献的アプローチを用いどうにか元暁の名を借りた誰かが書いたであろうという主張を展開することで対抗してきたが、ここで重要な「なぜあえて元暁の名を借りたのか」、という理由については憶測を羅列するだけで証明になっていない(※そもそも元暁が書いていないという立証にも至っていないのだが)。
また社会科学的アプローチの基本を踏まえ、偽撰説にさらに批判を加えるとすれば、「頭の中はわからない」という批判も付け加えられる。偽撰説を唱える学者の中に、約800年〜1300年前の高僧の頭の中を勝手に決めつけて書いている学者がいる。例えば、明恵が『遊心安楽道』を元暁撰と誤認していた、というような指摘は科学的でもなんでもない。その時、明恵がどのように認識していたのか、というものは誰にもわからないし、そのようなものは科学的に証明できない。
最後に、偽撰説を唱えた学者の宗教的背景として、鎌倉新仏教以後成立した日本における浄土関係の宗派との関わりが存在する場合、偽撰説には排外主義と植民地主義が内在している可能性すらあるということも指摘しておきたい。
この『遊心安楽道』、浄土宗の祖、法然上人が『選択本願念仏宗』において、浄土宗が成立する論拠として第一に挙げている。
「浄土宗の名その証一に非ず。元暁の『遊心安楽道』に云く、浄土宗の意は本、凡夫の為にし兼ねて聖人の為にす」、「華厳にまた菩提心有り。彼の『菩提心義』および『遊心安楽道』等に説くがごとし」(『選択本願念仏集』)
具体的に、遊心安楽道ではこのように記述している。
「四十八の大願、初にまず一切凡夫のため、兼ねて三乗の聖人のためにす。ゆえに知んぬ。浄土宗の意は本凡夫のため、かねては聖人のためなり(『遊心安楽道』:又四十八大願。初先爲一切凡夫。後兼爲三乘聖人。故知。淨土宗意。本爲凡夫。兼爲聖人也。)」
これにはなぜ出家できる業縁を持たず、戒律を持たず、行を修せない衆生(凡夫)こそが救われるのか、という浄土宗の核心、すなわち悪人正機が明白に説かれ、悪人正機を唱える浄土教がなぜ宗として成立するかも明らかにされている。
これを元に良忍・法然(※どちらも秦氏出身の遊行僧)が各々融通念仏宗と浄土宗を日本で興した(※法然は善導を強調したとすれど)。
また戒律は「守って守り、破って破り、守って破り、破って守る」として7世紀にすでに肉食妻帯をし、仰信(菩提心)と十念に基づく民衆仏教に努めた元暁大師の生き様は、親鸞聖人の先駆けともいえる(善導は、元暁のように浄土教の実践するために破戒をし、非僧非俗するまでに至っていない)。
要するに、元暁大師の浄土思想とその実践は日本で花開いたのである。
この元暁大師の華厳浄土宗のエッセンスが、『遊心安楽道』には詰まっている。智光 合掌
統国寺(古寺名:百済古念佛寺)
〒543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-31
TEL:06-6771-5600 FAX:06-6771-1236