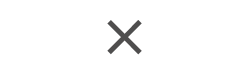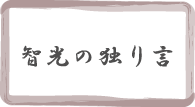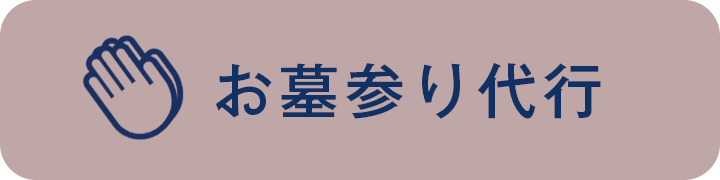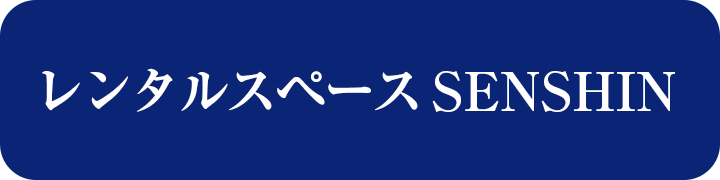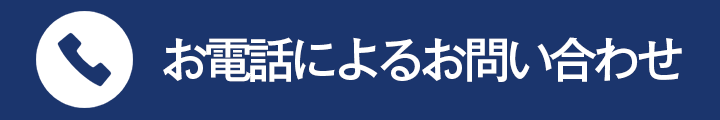第六十六回「心を真ん中に その2」~映画「悪人」を観て
久しぶりに映画を観た。
主演女優が海外の賞を獲ったという触れ込みをもさることながら、やはり「悪人」というタイトルがこの映画を選んだ決め手だったように思う。
(この先はネタばれ注意です。悪人を見ようとお考えの方は、ご覧になられてからお読みください。)
結論からいうと、この映画は世相を的確に反映しながら、人間とは何か、という事を見事に描いている。
内容は期待通り。
この映画のキャッチフレーズになっている「誰が本当の悪人なのか?」という問いの答えが、非常に仏教的なのである。
誰が悪人か?その答えは…
登場人物みなが悪人と言える。
語弊があってはいけないので、ここでの悪人の定義を明らかにしておきたい。
ここでの悪人とは、罪がある人。
逆に言えば、善人とは、罪がない人となる。
が、この映画で最も訴えていたのは、「すべての人が少なからず罪を背負って生きている」ということではなかったか。
…主人公の清水祐一は、好意を抱いていた女性に、ある時、馬鹿にされ、罵られ、足蹴にされる。それも他の男性に足蹴にされたその女性を祐一が助けてあげようとしているのにもかかわらず。…ついにキレて我を忘れ、その娘を絞め殺してしまう。
そしてマスメディアは、人を殺したこの結果だけを一方的に流す。
このマスメディアの報道だけに接すれば、誰でも祐一は悪人そのものと断ずるだろう。
しかし、この祐一は幼少のころ、母親に捨てられた過去を持つ。また寝たきりの祖父と祖母の面倒を見ながら、長崎の小さな町でほそぼそと暮らしている青年だった。祖父の身体が悪くなったら、病院に連れて行くのも修一の役目。働き、風呂に入り、祖父母と食卓を囲む、このような平凡なサイクルが永遠に続くかのよう…。若い祐一はよく耐えていた。
この面を観ると、祐一は善人ではなかろうか。
次に祐一に殺された若い女性~石橋佳乃。
彼女はまじめな両親の下に生まれ、博多で保険の仕事をしているOLだ。若い娘がゆえに、恋愛中心の生活。が、一方で今時の娘らしく恋愛へのドライさも併せ持っている。
恋に、仕事にひたむきな普通の娘。
この面では、決して悪人とはいえなかろう。
しかし、彼女は祐一と関係がありながら、祐一を常に蔑んだ目で見ている。また本命は他~増尾~にいる。祐一に殺された夜も、元は祐一と約束していたのに、偶然通りかかった増尾の車に乗り込んだことが事の発端であった。それも祐一が見ているその目の前で。
この夜、彼女の心はあることを契機に非常に荒れる。そしてむしゃくしゃしていた彼女は祐一に下記のような趣旨のことを直接言い放つ。
「私、あんたみたいなのと付き合うような女じゃないっちゃけん!」、そればかりか助けようとしている祐一に「レイプされそうになったっていってやる」
この言葉が祐一を錯乱させ、心の中の悪が増幅させられる。そして、最悪の結末となった。
この言葉を吐いた瞬間の彼女の心の中には悪意が満ちている。まぎれもなく悪人だ。
では、彼女がこのような罵詈雑言を祐一に容赦なく浴びせかけた契機とはなんだったのであろう?
それは、佳乃が思いを寄せる増尾から、同じようなことを言われたからだ。
「増尾君の実家って、湯布院の老舗旅館なんやろ。…なんか、女将さんって大変そう。」
佳乃がまだ一度しか会った事がない自分の車にのこのこと乗りんこんだ事に苛立っていた増尾。さらに極めつけは佳乃の餃子のにおい…ついに増尾は切れて言う。
「…別にあんたが心配することなかよ。…だげん、あんたとうちのおふくろは女のタイプが違うってこと。あんたはどっちかって言うたら仲居タイプやない?まぁ、もしうちの旅館で働くことがあったらの話やけど」
そういって、佳乃を車外へ蹴りだす。
この瞬間の増尾は悪人だ。
ぼんぼんの増尾はこの映画を通じて、貧乏人をいつも見下している。が、いざという時は何もできないへたれの悪人に描かれている。
彼がこの性格を持つに至ったのは彼の努力が足らないからとまずいえる。
半分はそうだろう。
そう、半分は自分の責任、人は生まれもった素質と運を伸ばせるかは自己の努力が不可欠である。
しかしもう半分は親の責任ともいえる。
さらに正確を期すならば、縁~環境~の影響によるといえようか。
たとえばどのような環境に生を受けるか。大きく観れば、この戦後65年が経た平和な日本という空間と時代が彼をつくった。小さく観れば、湯布院の老舗旅館のぼんぼん、この環境の中に入れば、人は少なからず増尾のような性格を持つにいたる。
事実、この悪人の小説版では、増尾は父親について触れている箇所がある。
この過去が増尾の女性観~俺さ、どっか貧乏くさい女のほうがいいのよね~に影響を与えている。
どのような環境を子に与えるかの多くの選択は、親によってなされる。特に子供の時分は。
この意味では彼も人生に翻弄されているに過ぎない。
では、逆に作品を通じて、まじめな善人に描かれている人物らはどうか?
まず、佳乃の両親。
小さな床屋を経営している、ごく普通のまじめな両親。
彼らには何の罪もないように見える。表面上は。
しかし先述のように、子の責任の半分は親にある。
博多で働く娘をほったらかしにしておいたこと…、これが本当によかったのかどうかは結果によって判断される。
また娘の死を聞き、錯乱した佳乃の父親は妻を責める。
後にそれを後悔し、謝るのだが、その責めた瞬間は父親は妻に対して罪をつくったと観られる。
次に祐一の育ての親のおばあちゃんはどうか?
一生懸命母親に捨てられた祐一を育て上げたおばあちゃんには、一見何の罪もないように見える。ましてや小説では、彼女は戦争の中、あらゆる苦労をしてきたと描かれている。
しかし、人生は四苦八苦。人生に苦は尽きない。いくら何かの信仰を持とうと。まじめに生きてきたからといって、苦がなくなるわけではない(逆にあらゆる悪事を尽くそうと、当然苦がなくなるわけでもないが。)。彼女の人生にも苦が続く。極めつけは大事に育てた孫が殺人を犯したという苦であった。
しかし酷なことのようだが、彼女にも祐一が殺人を犯すに至った一因がある。
…祐一の人間性を形作る上で決定的な要素となったのは、祐一の母親が祐一を捨てたこと。その母親は彼女の次女。つまり祐一のおばあちゃんの子だ。ここに一つおばあちゃんの罪を見て取れる。
あと、若い祐一を田舎町に閉じ込めていたのもおばあちゃんの都合が大いにあったように感じられる。おばあちゃんはいう。
「しっかし、わが娘のせいとはいえ、祐一がうちにおってくれて、ほんと良かったよ。これで祐一がおらんかったら、じいさんの送り迎えだけでも、ふーこらめ遭うところやった」
祐一が佳乃のように博多へ出ていたら、少なくとも自分の感情をうまくコントロールできず、ストレスをためこみ、ふとしたことで我を忘れてキレてしまう祐一ではなかったように思う。
ちなみに、祐一を捨てた母親の罪について考えてみよう。
母親にはもちろん罪がある。そしてそれを自覚している。
しかし、小説版にはそれに対しての彼女なりの言い分が書かれている。
その言い分の一つはあの祐一~殺人を犯した~を育てたのは、私じゃなか、という事。
もう一つは、祐一とは年に何度か会っていた事。そしてその時、祐一に金をせびられていたことだ。彼女の目からは、罪は十分償ったと見えている(結局、祐一は欲しくもない金をわざとせびっていたのだが…)。
ここで興味深い対照的な描写。
博多に出た佳乃、長崎の田舎町に縛られる祐一。
しかし、ともに結末は悪かった。
…これが人生の妙なのだろう。
計算し尽くして、これがベストの答えと思い、一つの選択をしたとしても、そしていかなるプロセスを一生懸命に踏んでも、結果はその時までわからない。
半分は自分の責任、もう半分は環境の責任。
たとえば、親は選べないが、どの親の下で育つかということは人生において決定的なことだ。どのような親を持つかだけではなく、友達を持つか、どのような先生に出会うか、事故にあうか、あわんか、いつ挫折するか…。それだけでなく、どのような時代に生まれるか。戦争の時代に生まれるか。あるいはこの平和な日本に生まれるか。どのような縁を与えられるか、で人生は大体決まる。
しかし残念なことに、縁は自分で選べない。
あと、結果は努力の量に比例しない。
まじめ一徹の人が必ず幸せになれるのか?
残念だが、この現実にそのような保証はない。
ただ幸せに生きている人はみな努力していることには違いない。が、幸せになるために必要な一定の量というものは存在しない。
とどのつまり、これはもう…
「運」でしかない。
なぜ祐一と佳乃の人生が最悪の結末を迎えたかという問いの答えは、ただ運が悪かったとしかいいようがないのではないだろうか。祐一のように親に捨てられても、それをばねにひたむきに生きて幸せになっている人もいるし、また佳乃のように自由気ままに生きて幸せをつかんでいる人もいるのだから。
ここに人生の難しさがある。が、この真実を観たとき…
人は祈ることの大切さを知る。
お釈迦さんは、まずすべてが縁に因る、ということに気づかれた。これにまず言及しながら…
環境は変わる。そして変わり行く環境の前では人は基本的にただただ受身、つまり人の心は環境の影響を大きく受ける、と指摘された。
しかし、これがお釈迦さんの結論ではない。
お釈迦さんの至った結論は…
自分で心を真ん中にする努力はできるということだった。
が、これには一つ条件がある。
…自分をあるがままに見つめなおすこと、これが肝要だ。
さて、最後にヒロインの馬込光代。彼女に罪はあるのか?
祐一は彼女との日々を通じて、はじめて真っ暗な人生の中で光を見、人生の温かさを感じる。
この意味で、彼女は絶対的な善のように感じられる。
しかし、自首することを決め、警察署へ向かう祐一を最後に引き止めたのもまた彼女だった。二人とのふれあいの中で、初めて人生に光を見たのは祐一だけではなかったのだ。
祐一が捕まってしまえば、また自分は一人ぼっち。あの孤独の闇に戻るのはいやだ…。
ある種の欲が彼女にあのクラクションを鳴らさせた。
…ここに彼女の中のやるせない罪がある。
人間にはみな罪がある。
考えてみれば…人間はそもそも罪なしには生きられない存在だ。
何かを犠牲にして、私たちは生きている。何かの犠牲なしには人は生きていくことはできないのだ。
たとえベジタリアンだとしても、他の命の上に自分の命があることに変わりはない。
また人は環境が変わる中で、善人にも、悪人にもなれる。
この意味では、絶対的な善や悪などは存在しない。
善悪は常に混在している。ただ善悪のどちらが、表に顔を出すかは、そのときの環境~縁~による。
自分をあるがままに見つめるとき、人は自分の中の罪に気づく。
そして、自分の不完全さを受け入れたとき、人を思いやる心の芽が出てくると私は思う。
自分も不完全であり、色んな癖がある。昔の人はよく言った。人は「なくて七癖」なのだと。
だから、相手も不完全であり、色んな癖があって、当たり前だと気づく。
こうして慈悲の心が芽生え、自分と他を俯瞰して観られるようになった時、第3の眼が四苦八苦な人生に光を照らす。
一方で、自分を罪のない完全な存在と思うとき、人は幸せを見失う。
人生うまくいっているときはいいが、うまくいかなくなったとき、心が大きく振れ、動揺を隠せない。「なぜうまくいかないのか。まじめに生きているのに、がんばっているのに、努力しているのに、…自分は完璧なのに。」
ここでポイントは、人生は諸行無常、環境は変わり行くということだ。
言い換えれば、人生の中で必ず悪いときはやってくるということ。
永遠に「運」があるときは続かないのだ。
まじめに生きるだけでは幸せになれない根本がここにあるのかもしれない。
まじめに生きることは幸せになる上で必要だ。しかし、その行為自体に囚われ、自分の中の罪を見失ってしまい、自分の中の善にだけを見てしまっては、幸せを見失う。
この答えの一つは、この世自体がもともと、善悪が混在しているからである。
悪はいつの世にもある。もっと言えば、悪がなければ、善はない。つまり善と悪の間には上下はない。ただプラスとマイナスの関係に過ぎない。
またまじめに囚われ、自分の努力で何でもできると勘違いし、縁の大切さを忘れてしまっても、だめだと思う。
縁の中で、自分は悪人であり、善人でもある、という認識を持つとき、心が真ん中になりはじめる。そして、その状態の中で、人生を観たとき、人は生きる力を得られる。
…事件後、毎日執拗なメディアの取材攻勢に遭う祐一のおばあちゃん。何を思ったか彼女はだまされて高く売りつけられた漢方薬の代金を取り返しに行く決心をする。勇気を振り絞って、一人で事務所に入る。もちろん返してもらえない。絶対的な戦闘力の差。チンピラの一人がおばあちゃんを事務所からたたき出そうとする。が、彼女は事務所のいすにしがみつきながら、叫ぶ。
「これまで必死に生きてきたとぞ。あんたらなんかに…、あんたらなんかに馬鹿にされてたまるもんか!」
また佳乃の父親は、増尾に復讐しようとするも、返り討ちにあう。
大きい増尾、小さい佳乃の父親。
誰が見ても、佳乃の父親に勝機は限りなく小さい。
でも、立ち向かう。
殴り殺そうと考えていた増尾を目の前にしながら、スパナを下ろして、佳乃の父親は言う。
「…そうやってずっと、人のこと、笑って生きていけばよか」
自分の中の善悪、そして環境の変化に対しての無力。
それを認識し、逃げずに立ち向かったとき、人は間違いなく、光を感じる。
仏教的に言えば、極楽浄土への一歩を踏み出していると私は思う。
いやその瞬間にすでに阿弥陀の光の中にあるのかもしれない。
合掌
追伸:光~悟り~は近づけば消える陽炎のよう。
これに気づいたとき、初めて金剛となる門が開かれるのかもしれないと思う今日この頃。
統国寺(古寺名:百済古念佛寺)
〒543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-31
TEL:06-6771-5600 FAX:06-6771-1236